分野横断で協働できる若手育成の場をつくりたい
——『情報戦、心理戦、そして認知戦』を2023年12月に刊行してからの反応は?
佐藤
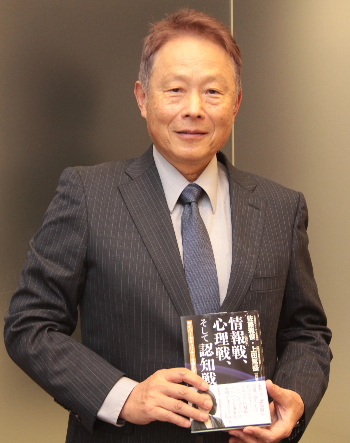
日本ではまだ「認知戦」という言葉がほとんど知られていないし、定義さえされていない状態なので、あえてそこにチャレンジしました。出版後、講演やメディア出演の依頼がいくつも入りました。サイバーセキュリティアワードの受賞が引き金となって、より幅広い層の方々に関心を持っていただけたと感じています。
——一般の人々が知らない国家レベルのサイバーセキュリティ最前線を、ファクトに基づいて丁寧に描写された大作ですね。
佐藤
ありがとうございます。全400ページにわたり、書きたいことを書き込めたと思っています。政府に対するちょっと辛口のコメントも入っています。サイバーセキュリティに関して、「偽情報」とか「誤情報」といったことに対する関心が高まってきているのですが、全体を俯瞰してみるとかなり矮小化された議論になっていることが多いと思います。本来考えるべきことの半分くらいにしか目が行き届いていない。特に、「認知戦」のような戦争の手法が現実に使われ始めていることについてはほとんど知られていません。端的に言えば、プロバガンダや心理戦などを駆使して相手(敵国の国民)の認知、あるいは世論を自在に操ろうというものです。気付かないうちに敵の術中にはまり、戦わずして負けてしまうのです。サイバー攻撃が「システム」だけでなく「人間の脳」をも攻撃対象として拡大しているのです。ところが、そうした世界の現実に対して、日本政府も日本国民もあまりに無関心・無頓着で、非常に強い危機感を抱いています。そこに警鐘を鳴らすことが本書執筆の最大の動機です。とはいえ、認知戦に関する研究が本格化したのは2017年頃からです。対抗策を練るためには、まず相手を知ることから始めなければなりませんが、中国の認知戦のやり方、ロシアの認知戦のやり方などの分析はまだ緒に就いたところです。歴史的な考察と合わせて分析・研究を深めていく必要があります。また、ナチスのヨーゼフ・ゲッペルスは「嘘も100回言えば真実になる」と言いました。プロパガンダに扇動されないためには、間違った主張に対しては都度しっかり反論することが重要なのですが、それは日本人が不得手とするところかもしれません。
——佐藤さんは自衛隊ご出身で、2014年に新編された自衛隊指揮通信システム隊の初代・サイバー防衛隊長も務められた後、民間のセキュリティ会社に籍を移されました。それぞれの立場で見える風景は違いますか?
佐藤
自衛隊のサイバー防衛隊は、基本的に自衛隊・防衛省のシステムを守ることが最優先任務であり、サイバー攻撃を被った民間企業を助けるといったところまでは対応できていません。そのため、民間企業がどのようなサイバー攻撃を受けているのか、何がどのくらい起きているのかということについて、実は正確に把握できていませんでした。民間企業に移って、国の組織・機関と民間企業では受けるサイバー攻撃のタイプが大きく異なることを実感しました。同時に、民間企業が向き合っているのは、サイバーセキュリティ全体の中ではとても小さな部分だということにも驚きました。端的に言えば、認知戦の脅威に関して民間企業はあまり関心が高くありません。また、国の省庁にしてもそれぞれがバラバラに対応している状況です。これは日本だけではなく、世界各国が同じような課題を抱えているようです。国家に仕掛けられた認知戦に対して、省庁単位で立ち向かうことはできません。やはり、関係省庁が密に連携し、政府全体で対処することが必要です。さらに、民間との連携も検討する必要があると思います。本書にはそうしたメッセージも込めたつもりです。
——今後の活動の焦点は?
佐藤
力を入れたいのは後継者の育成、若者の育成です。サイバーセキュリティにとどまらず、地政学、心理学、法学、経済学、国際関係論など様々な分野で活躍している若手の知見・英知を結集し、AIも活用しながら、認知戦への備えを厚くしていく必要があると思っています。いろいろな気づきを話し合ったり、チームとしてコラボレーションしたりできる場を提供し、後輩諸君が実力に磨きをかけてもらえるようなスキームをつくることが、今の私の願いです。
——大変重要な取り組みですね。実現を祈念しています。
他のインタビュー
















情報戦、心理戦、そして認知戦
作品紹介サイト
サイバーセキュリティアワード2023(授賞式は2024年3月15日に開催)の受賞者に“その後”を聞くインタビュー・シリーズ。書籍部門 優秀賞を受賞した『情報戦、心理戦、そして認知戦』を執筆した株式会社ラック サイバー・グリッド・ジャパン ナショナルセキュリティ研究所長の佐藤 雅俊さんは、「サイバーセキュリティにとどまらず、地政学、心理学、法学、経済学、国際関係論など様々な分野で活躍している若手の知見・英知を結集する場をつくりたい」という構想を描いている。(聞き手はサイバーセキュリティアワード事務局、以下敬称略)