サイバースペースの分断を回避するために
小宮山 功一朗さんに聞く
——書籍部門 最優秀賞、おめでとうございます。
小宮山

大変嬉しかったです。共著者の小泉 悠さんも、出版社の方もとても喜んでいます。小泉さんは他でもいろいろな賞をもらっている方ですが、今回のサイバーセキュリティアワードは審査委員の皆さんがその道のプロフェッショナルなので、「プロに評価される著作を残せたことが誇らしい」とおっしゃっています。 このアワードがユニークなところは、書籍、ウェブサイト、映像・アニメ、企画ものなどバラエティーに富んだコンテンツを横並びにして審査するところだと思います。例えば大賞の『こうしす!』を拝見して、「ああ、こういうアプローチでもサイバーセキュリティを世に知らしめることができるんだな」といった新鮮な発見がありました。 授賞式後の懇親会でも、『こうしす!』の監督さんや出版各社の編集者さん、セキュリティ芸人のアスースン・オンラインさん(前回受賞者)などクリエイティブな方々とお話する機会を得て、良い刺激を受けました。自分自身の領域とは遠いところにあるというイメージだったのですが、目指すところはわりと近しいなと。この気づきが得られたことは、当初想定していなかった嬉しい誤算です。
——サイバースペースを可視化する本書のスタート地点は?
小宮山
以前、テレビ局の人に「サイバーセキュリティは絵(映像)にならない」と言われたことがありました。絵にならないから報じられない、だから一般の人たちの理解が進まない、知らなくても大きな問題ではないと見なされているという状況に忸怩たる思いがあったのです。それをなんとかするためには、自分の足で歩いて、モノを実際に見て、発見したこと感じたことを書き連ねていくという表現方法にチャレンジしてみようと思ったのがきっかけです。 私は長くサイバーセキュリティの専門家として活動してきましたが、専門知識を持たない一般の方々に届く表現力、ボキャブラリーという点でちょっと心許ないところがありました。それが小泉さんと一緒にやりたいと考えた理由です。小泉さんは軍事や地政学の専門家で、多彩な表現力と物事の本質を見通すセンスを持たれていて、何冊ものベストセラー本を書かれています。そんな人と旅して回ったら面白そうだなと思ったのがスタートでした。 早川書房の編集者、石井広行さんを含めた3人での最初の会議で私が用意した企画書のタイトルは、『サイバー空間ぶらり旅(仮)』でした(笑)。いいじゃないか、やろうやろうと盛り上がり、とんとん拍子に企画が固まっていきました。
——サイバースペースの重要な構成要素であるデータセンターの巨大さには驚かれたようですね。
小宮山

IT技術者をやってきたので、「データセンターとはこういうもの」というイメージは自分の中に持っていました。オフィスビルみたいな建物の中にストレージのラックが並んでいて、空調でがんがん冷やされているといった。ところが、そういうイメージをはるかに超えて個々のデータセンターは巨大化したのです。分かりやすく言うなら、イケアやコストコのような巨大商業施設をしのぐサイズです。そうした巨大データセンターがある地域にいくつも密集している。遠くから見ると、要塞のような、丘のような、建物と言うのが憚られるような大きさにまでなっています。 ところが、そんな巨大なものが意外と近くにあるというのに、我々は普段そのことにあまり意識を払わずに生きているわけです。それは、我々が知る努力を怠っているという側面もあるかもしれませんが、より本質的にはデータセンター企業が自らの存在をなるべく世に知られないように静かに息を潜めているからです。巨大データセンターの中には無数の顧客の膨大な量の重要データが詰まっているだけに、「ここにデータセンターがあります」「弊社は全国〇拠点で運用しています」などと明からさまに宣伝する類のものではありません。データセンターは自らを隠そうとするのです。今回の取材で何度もそう感じました。
——海底ケーブルの敷設船にも乗られましたね?
小宮山
はい、ケーブル敷設船の大きさにも驚きました。小泉さんとふたりで「かっこいいなあ」ってしみじみと(笑)。研究者の仕事って、基本的には本を読んで、文字を書いて、 時には人と議論して、というところですが、それに比べて7階建てビルくらいの巨大な敷設船が動いているのは壮観の極みでしたね。 海底を這わせる光ファイバーケーブルの実物も見せてもらったのですが、逆に、その細さに驚きました。「こんな頼りない線で日本と海外が繋がっているのか!」とみなさん驚かれると思います。 有事の際には、狙われていとも簡単に切られてしまうでしょう。日本および東アジアの安全保障環境は、5年後、今よりも厳しくなっているでしょうから、「謎のケーブル切断」みたい事件がいくつも起こるんじゃないかと思います。 どこの国によるものかは分かりませんが・・・。 そういう未来に備えるうえで重要なのは、切られないケーブル開発というような無理な方向に向かわず、切られてもなんとかなるようなレジリエンス(回復力)の強化を考えることです。切られても通信が途絶することがないように、例えば即応修理のための能力を強化するとか、衛星通信などの代替手段を準備するとか、そちら向きにフォーカスしてほしいと思います。
——本書を通して、一般読者に最も伝えたいことを改めてお伺いできますか。
小宮山
20年くらい前まで、我々はこう言っていました。 「これからはクラウド・コンピューティングの時代だ。 サーバーを自分で置いたり、手元にデータを持ったりするのは時代遅れ。スケールメリットを出せる専門事業者に任せて、使いたいときに必要なだけ使うというのがこれからの情報システムのセオリーだ」 それが嘘だったとまでは言いませんが、クラウド・コンピューティングという言葉の意味は再考されるべきです。これだけ世界が分断しているというのに、大手のクラウド・サービス・プラットフォーマーはアメリカと中国に集中しています。日本やヨーロッパ各国はこれからどうするのか。無思慮にデータを預け続けるということは難しくなり、クラウド依存を見直す機運が高まっていくと思います。 かつては、データセンターのような物理的インフラなんてどこにあってもいい、どこにあるかを議論する意味はないというのが定説でした。でも今は、「どこに在るか」という地理的比重がどんどん大きくなっていて、クラウドという発想が説得力を失いつつあるのです。千葉県印西だ、大阪だと言って場所にこだわっていることは、かつては時代遅れでしたが、今は重要な意味を持っている。本書を通して、そういう時代の逆行を知ってもらえたら良いなと思っています。
——世界の分断は、サイバースペースにも大きく影響を与えるということですね?
小宮山
世界が1つではないならば、サイバースペースも1つではいられないでしょう。 私自身、研究者としての関心がそういうところにあります。今後、世界は何分割され、インターネットはいくつに分割されるのか――。米中に分かれるだろうということが安全保障の世界では言われていますが、私自身はヨーロッパ型インターネットという考え方が浮上してくるのではないかと思っています。ヨーロッパの人たちは例えばプライバシー保護などにおいてアメリカとは相いれない思想を持っています。物理的に分離するのではなく規制や課税のようなかたちで制限が加わっていくのでしょう。 日本はと言えば、ヨーロッパと協力して第三極をつくる存在であるべきだとは思っていますが、現時点では明確なことは言えません。
——国連主導のインターネット・ガバナンス・フォーラム(IGF)でも「インターネットの分断回避」が議題になるほどですから、リアリティがあります。
小宮山
私は2024年12月にサウジアラビアで行われたIGF会合に出席しました。そこで感じたのは、インターネットをどう管理していくかという議論に対する日本を含めた西側諸国の関心の低さ、それとは対照的に、この問題に対する中国の熱心さ、その間の強烈なギャップでした。 IGF会期中、AIとサイバーセキュリティに関するセッションでのことです。中国の研究者や政府関係者がスピーカーとして登壇していました。聴衆は私も含めて30~40人くらい。リアルとオンラインのハイブリッド開催で、中国のオンライン参加者に質問権が回ってきました。カメラが切り替わってスクリーンに映し出されたのは中国のどこかの大学の大講堂でした。質問者の後ろでは大勢の中国人学生がセッションを聴講していました。 中国の優秀な大学生が100人単位でその議論にリアルタイムで参加していたことに、心底驚きました。自国に有利なインターネット秩序をつくることに膨大な人的リソースを投入している中国に対して、自律・分散・協調という基本理念に則って自由で開かれた空間として発展してきたインターネットを守るため、はたして日本の努力と貢献は十分なのだろうか・・・。正直、そんなふうに感じました。
——健全なサイバースペースを守るという意識と行動が大切ですね。
小宮山

おっしゃる通りだと思います。 取材の旅の余談なのですが、写真は「海魂の碑」を前に献花している小泉さんです。長崎でNTTのケーブル敷設船を取材させてもらったときのものです。 先の大戦で、通信インフラを担った方々の中には、命を落とされた方が少なからずいらっしゃいます。通信インフラそのものや海底ケーブルを敷設する船が狙い撃ちにされたからです。NTTの方々は、日々、お花とお供えを絶やさぬようにしているそうです。 サイバースペースを守るという仕事の重みを感じました。サイバーセキュリティと安全保障について研究している者として、そうした歴史の教訓をしっかり受け止めなければならないと思いました。
——貴重な体験談をいただきありがとうございます。改めまして、このたびのご受賞おめでとうございました。
他のインタビュー
-

Interview File No.12
精緻な損害推計が適切な対策を促す
こうしす!井二さん
-
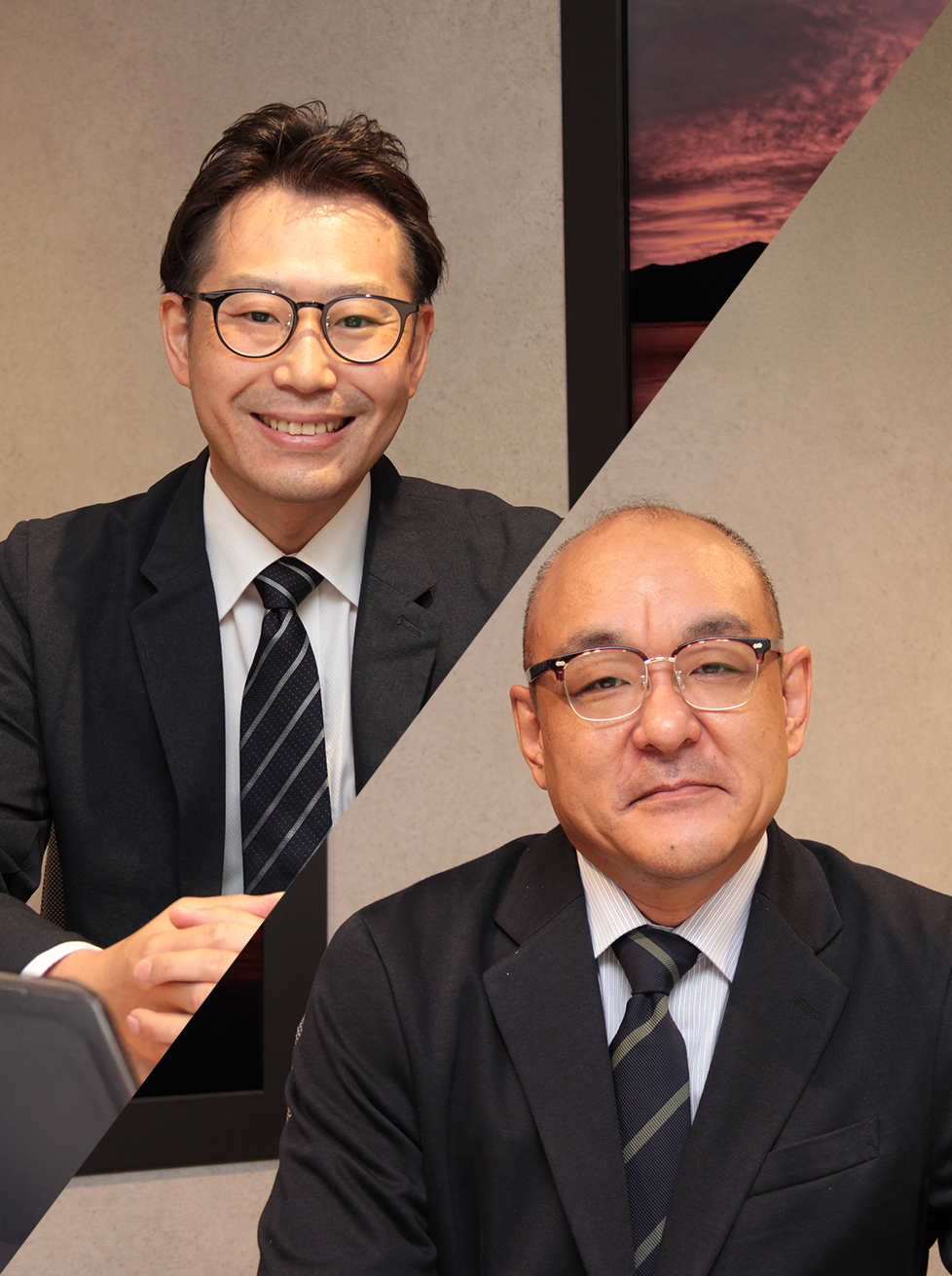
Interview File No.11
精緻な損害推計が適切な対策を促す
JNSA 神山太朗・西浦真一
-

Interview File No.9
人の弱点を知ることからセキュリティ啓発は始まる
ラック 吉岡






サイバースペースの地政学
小宮山 功一朗、小泉 悠 著、早川書房 刊
インターネット上に広がる「サイバー空間」とはそもそもいかなるもので、世界はどのように繋がっているのか――。そうした問題意識を基に、共著者の二人が、千葉に林立する巨大データセンター、日本サイバー史の重要地点・長崎、人知れず活躍する海底ケーブル船、北の大地のAIデータ拠点、そしてロシアの隣国エストニアに足を運び、サイバー空間の「可視化」に挑んだ現場ルポ。
作品紹介サイト
作品紹介サイト
サイバーセキュリティアワード2025の表彰式が3月3日に開催され、大賞1件、部門別最優秀賞4件、部門別優秀賞9件の栄誉が称えられた( 表彰式レポートはこちら )。書籍部門 最優秀賞に輝いた『サイバースペースの地政学』の共著者である 慶應義塾大学SFC研究所 上席所員 小宮山 功一朗さん に執筆の狙いを聞いた。(聞き手はサイバーセキュリティアワード事務局、以下敬称略)